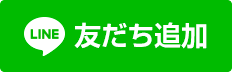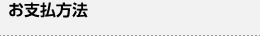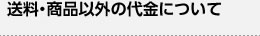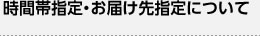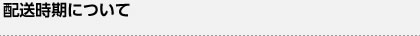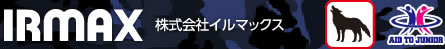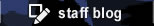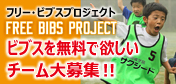スタッフブログ
朝日信用金庫様の「地元応援団+朝日Vol.294」にイルマックスが紹介されました。

サイクリングはユニフォームにこだわった方がいい?ユニフォームのメリット
サイクリングをしている方の多くは、こだわりのユニフォームを着ています。またサイクリングサークルなどに所属し、自分の所属しているチームのユニフォームを着てサイクリングを楽しんでいる方もいます。そんなサイクリングのユニフォームですが、こだわることでさらに楽しむことができます。どうしてサイクリングはユニフォームにこだわるべきなのか、詳しく解説していきます。
1.サイクリングはユニフォームが大切
サイクリング、特にロードバイクを楽しむ方が増えています。レースなども様々な場所で開催されており、休日には景色のいい一般道を走る自転車をよく目にします。ロードバイクは爽快感が魅力で、本体がとても軽いので空気抵抗が少なく、体感速度を楽しむことができます。
そんな爽快感を楽しむスポーツだからこそ、サイクリングにはユニフォームがとても重要です。通勤通学で自転車に乗ってきたという方が多いかと思います。学生の頃は車がなかったから仕方なく学生服や私服で自転車をこいで、移動手段としてしか自転車を見ていない方がほとんどです。しかし、サイクリングは一般的な自転車とは違い、スピードも体感も違います。
一般的な自転車であれば服装もそこまでこだわる必要はありませんが、ロードバイクをスポーツとして楽しむのであれば、走行中いかに快適にサイクリングを楽しめるかが重要なポイントになります。普通のジャージや服装では、残念ながらせっかくスピードを体感することが難しいです。サイクリングはユニフォームにこだわることでサイクリングの魅力である爽快感やスピード感を何倍にも楽しむことができます。
2.専用ユニフォームを着るメリット
サイクリングをより安全に楽しくためにはユニフォームは非常に重要な役割を果たします。サイクリングのユニフォームを着るメリットについて解説していきます。
2-1.身を守る
サイクリングのユニフォームは原色などデザイン性の高いものが多いです。ロードバイクは一般道を走るため、車から認識されることが安全面でとても重要です。ですからサイクリングをするときはユニフォームを着ると安全性が高くなります。
2-2.快適なサイクリング
サイクリングのユニフォームは体型にぴったりしています。そのため、風を感じやすく、サイクリングしているときは爽快です。また一般的な服装では速度が早くなればなるほど、風が入って危険です。快適にサイクリングをするためにもユニフォームのメリットが大きくなります。
2-3.軽減負担
サイクリングのユニフォームは体の負担を軽減してくれます。ロードバイクは一般的な自転車よりも構造的に乗り心地があまりよくありません。乗り心地が硬いことで加速し、サイクリング中の振動がもろにお尻に伝わってきます。ユニフォームは振動を緩和する機能もあるため、体の負担を軽減してくれます。
3.上半身はどんなユニフォーム?
サイクリングのユニフォームは具体的にどんなものがあるのかご紹介します。まずは上半身のユニフォームについて解説していきます。
3-1.サイクルジャージ
サイクリングのジャージは汗をしっかりと吸収する素材でできています。ピタッと体にフィットして、サイクリングを快適に過ごすことができます。半袖で様々なデザインがあります。
3-2.アームカバー
怪我をしないために腕もカバーします。アームカバーをつけることで夏は日差しを予防し、冬には暖かくしてくれます。直接腕に風が当たると体力も消耗しやすいですが、アームカバーをつけることで体力面でもサポートしてくれます。
4.下半身はどんなユニフォーム?
サイクリングのユニフォームについて下半身のユニフォームはどんなものがあるのかご紹介していきます。
4-1.サイクリングパンツ
サイクリングパンツは、サイクリングの振動を軽減するためのパッドが入っています。普通のズボンよりもフィットしてこぐときの抵抗がありません。UVカット機能や温かい裏起毛素材などで作られています。特にサイクリング初心者はパッド付きでサイクリングを楽しみましょう。
4-2.レッグカバー
足もむき出しでも空気が足に直接当たって、足を怪我するのを防止するのがレッグカバーです。速度が出ているので万が一転倒しても怪我を軽減してくれます。UV機能や裏起毛で冬はあったかい使用があります。
5.まとめ
サイクリングのユニフォームはただおしゃれを楽しむだけにあるのではありません。サイクリングの爽快感をより楽しめたり、体の負担を軽減したりと非常に役立っています。さらにデザイン性の高い原色の色が使われていることで、車から認知されやすく、交通事故防止にもなります。
サイクリングのユニフォームはオーダーメイドすることもできます。圧倒的なコストパフォーマンスでユニフォームを作るなら、ぜひ「イルマックス」にお問い合わせください。サイクリングをより快適にするオーダーメイドユニフォームを作れます。「イルマックス」はあなただけのユニフォームをお作りします。
ボルタリングはユニフォームで何倍も楽しくなる!ユニフォーム選びのコツ
東京オリンピックから公式種目として新たに追加されたボルタリングですが、多くの方が身近なスポーツとして挑戦し始めています。そんなボルダリングですが、ユニフォームにこだわることでもっと楽しめるといえるでしょう。そこで今回は、なぜユニフォームにこだわるとボルダリングが楽しくなるのか、その理由やボルダリングの服装について詳しく解説していきます。
- ボルタリングはどんなスポーツ?
2020年の東京オリンピックの新しい競技として今、注目を浴びているスポーツがボルタリングです。ボルタリングは腕の力だけでなく、いかに早く登るかについて頭を使うスポーツでもあります。ボルタリングは山登りではなく、人工的に作られた壁の突起につかまりながら登っていきます。
ボルダリングはただ壁を登っているだけのように感じるかもしれませんが、実は違います。ボルダリングはホールドという色のついた石を登っていくのですが、同じ目印があるホールドを登っていきます。つまり無数のホールドの中から指定されたホールドのみを使って登っていくため、何にも考えずに登っていくと途中で登れなくなってしまうこともあります。ただ登るだけでなく、スポーツとしてのルールもあるのがボルダリングの魅力といえます。
2.ボルタリングをするときの服装の注意点
ボルダリングのユニフォームについて解説する前に、服装についての注意点があります。特に女性の場合は、ボルダリングを始めるのであれば服装にまずは注意をしましょう。まずおすすめなのがジャージです。ボルダリングは上半身だけでなく、下半身も動かしてホールドを掴んで登っていきます。
そのためストレッチが効いていないと、大きく手足を動かすのが難しいといえます。またボルダリングはあまり動いていないように見えて、かなりのパワーを使うので大量の汗をかきます。速乾性のいい服装を選びましょう。また手にチョークという粉をすべらないようにつけるため、服が粉だらけになってしまいます。汚れてもいい服装にしましょう。
3.ボルタリングのユニフォームのポイント
ボルダリングではおしゃれなユニフォームを楽しんでいる方も多くいます。そんなボルダリングのユニフォームを選ぶときのポイントをご紹介していきます。
3-1.肌を露出させない
第一に選ぶときのポイントとして意識していただきたいのが、肌の露出を避けるということです。夏場では半袖半ズボンですることもありますが、基本的にはロングTシャツとロングパンツがおすすめです。ボルダリングでは、壁を登っている最中に肘や膝をぶつけてしまうことがあります。そのため、できるだけ露出を抑えることで傷を予防できます。
3-2.動きやすい素材
最近では体にフィットした素材のスポーツウェアが人気ですが、ボルダリングは基本的に体にフィットした素材ではなく、動きやすい素材のユニフォームを選ぶようにしましょう。ボルダリングは体を大きく動かすスポーツです。体にピタッと合うような服装は大きく手足を動かすことには向いていません。そのため、大きく腕や足を動かせるストレッチ性のあるユニフォームを選ぶようにしましょう。
3-3.速乾性
ボルダリングは体を大きく動かすスポーツですので、自分の思った以上に汗をかきます。汗をかいていると登るときにホールドを掴んでいる手が滑ってしまうことがあります。よりボルダリングを安全に楽しむためには、速乾性のいい素材のユニフォームを選びましょう。汗が乾きやすい素材を選ぶことで、より快適にボルダリングを楽しめます。
4.オリジナルユニフォームでボルダリングを楽しむ
ボルダリングのユニフォームの選び方のポイントをご紹介してきましたが、ボルダリングは自分だけのオリジナルユニフォームを作って楽しむのもおすすめです。また、サークルなどのチームに所属してチームでお揃いのユニフォームを作って、ボルダリングをグループで楽しんでいる方も多くいます。ボルダリングは人気が高くなってきており、スポーツ用品店でもおしゃれなデザインの服装が多くなってきています。
スポーツ用品店でおしゃれなユニフォームを楽しむのもよいですが、よりボルダリングを楽しむにはオリジナルユニフォームがおすすめです。大会などもあるので、オリジナルユニフォームでより一層、ボルダリングへの気合も入ります。オリジナルデザインは高そうなイメージがありますが、市販のものとほとんど変わらない値段でオーダーすることもできます。より一層楽しむためにぜひオリジナルユニフォームをオーダーしてみましょう。
5.まとめ
ボルダリングは東京オリンピックから新たに加わる公式種目であり、多くの方がボルダリングを始めています。ボルダリングは体を大きく動かすスポーツなので服装選びが重要です。動きやすく、速乾性のいい服装を選びましょう。特に最初は擦り傷をしやすいので長いTシャツ、ズボンを意識するのがおすすめです。オリジナルのユニフォームを作ることでよりボルダリングを楽しめることでしょう。
「イルマックス」ではボルダリングのユニフォームもコスパよく作れます。ぜひ一度お問い合わせください。
ドッジボールにユニフォームは必要?ユニフォームの選び方とは
小学校のとき運動として、ドッジボールをしていた方は多いのではないでしょうか。ドッジボールは小さい子から大人まで楽しめるスポーツのひとつで、競技としても認められています。ドッジボールの試合に出場することになったとき、ユニフォームについて考える方もいるでしょう。
この記事では、ドッジボールにおけるユニフォームの必要性と、ユニフォームの選び方についてご紹介します。
1.ドッジボールにユニフォームは必要?
ドッジボールには、授業などで行われる試合のほかに、日本ドッジボール協会が執り行う試合が存在します。通常のドッジボールであれば、ユニフォームがなくても試合が行えます。チームによってはゼッケンで参加するところもあり、気軽にできるスポーツです。
しかし、協会によるドッジボールの試合は、ユニフォームが必須となります。デザインなど細かく規定されており、異なっていると大会への参加ができません。国内のドッジボール大会は、基本的にこの規定に沿ったユニフォームが製作されています。
しかし、リーグ戦やその他の海外大会などは、異なる部分もあるので注意が必要です。ユニフォームの規定デザインは変化することもあるので、大会への出場が決まったら都度確認するようにしましょう。
2.ドッジボールユニフォームの規定
ドッジボール大会に出場するためには、ユニフォームの規定を厳守しなければなりません。カラーやデザインなどが決まっているので、確認することをおすすめします。ドッジボールでのユニフォームは、基本的にシャツとパンツの2つがポイントとなります。
2-1.ユニフォームの色について
ユニフォームに使用する色は、前面と背面は同じ色合いでなければなりません。また、シャツの下にアンダーシャツを着用する場合は、単色で無地のものと定められています。単色の無地であれば色や長さなどの指定はほとんどありません。
また、シャツ以外にパンツも同様です。パンツはシャツと同じ色合いでなくても良く、またデザインやブランドが異なっていても問題ありません。アームウォーマーやアームカバーを使用する場合も、アンダーシャツと同じ規定となります。
2-2.ユニフォームに表示するロゴについて
ユニフォームに表示するロゴや名入れは以下の通りです。
1.チーム名
2.所属都道府県名
3.メーカー名
4.広告
チーム名をユニフォームに取り入れる場合、前面の右胸か左胸、背面に記載することができます。サイズも決まっており、前面の左胸に取り付けるときは40平方センチメートル以内のサイズ、その他の位置は高さ6センチメートル以内、幅30センチメートル以下と義務付けられています。
チーム名は和名やアルファベット、イラストやマークなどどれでも問題ありません。しかし、表示はすべて同一のものにし、どこか1か所でも異なる表示にするのは禁止されています。
所属都道府県名はシャツの左袖か左胸の一か所に取り付けましょう。サイズは40平方センチメートル以内と決まっています。都道府県名でなくても、活動地域名が記載されていれば問題ありません。県や市、町の有無についても指定されていません。
メーカー名は、ロゴも使用可能です。シャツに取り付けるマークは、右胸か左胸の1か所となり25平方センチメートル以内で取り付けましょう。パンツに取り付ける場合は、前面と背面のどちらか1か所となり、シャツと同様に25平方センチメートル以内が望ましいです。
広告表示が必要なチームの場合は、協会が認めた企業と団体の広告のみ載せることができます。サイズはシャツの場合、右袖か左袖の1か所に40平方センチメートル以内でとりつけます。パンツには前面の左右どちらか1か所となり、20平方センチメートル以内の広告にしてください。
広告表示期間は、協会や主催大会の規定に準じます。
3.ユニフォームを選ぶ際に気を付けること
ユニフォームは規定に従って作成しましょう。ユニフォームを選ぶ際は、基本的にはオーダーとなります。依頼する際には、必ずここで紹介するポイントをしっかり守ってつくることをおすすめします。
3-1.チームでデザインは統一すること
公式大会に出場する場合、チームのデザインはすべて統一する必要があります。色やデザイン、シャツの形などもすべて統一しなければならないので、各自での依頼は不向きです。デザインが少しでも異なっていると、出場ができない可能性もあります。
3-2.必ず背番号を入れる
ユニフォームを作成する際は、必ず背番号が必要です。背番号は前面と背面に必要で、シャツを見たらすぐ分かるデザインにしなければなりません。色紙文フォントに注意しましょう。また、選手番号は1~20までの数字が使用可能です。
選手番号を表示する際は、前面の中央、上部が襟下5センチメートル以内、高さ12センチメートル以上20センチメートル以下の位置が義務付けられています。シャツの背面は、中央位置の上部襟下5センチメートル以内、高さ20センチメートルに取り付けましょう。
パンツに選手番号の取り付けは必要ありません。取り付ける場合は、前面の右側、高さ10センチメートル以上15センチメートル以内と決められています。
4.まとめ
ドッジボールは、気軽に楽しめるスポーツです。しかし、公式大会も存在しており、出場する場合は規定に沿ったユニフォームの着用が義務付けられています。ドッジボールの大会に出場するチームは、1着以上のユニフォームを所持しておきましょう。
「イルマックス」では、ドッジボールに使用するユニフォームの作成を行っています。昇華プリントを採用しており、発色がよくデザイン性に優れたユニフォームの作成が可能です。ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。
卓球ユニフォームの選び方とは?気を付けるポイントについて
学校の部活以外にも、趣味で卓球をやっている方は多くいます。学校で卓球を行う際は、体操服や指定されたユニフォームを着用することが多いことでしょう。しかし、趣味で行う卓球の場合は、普段の服装からユニフォームまで考える必要があります。
この記事では、卓球をするときに最適な服装や、大会などに出場する際に知っておきたいユニフォームの規定についてご紹介します。
1.卓球するときの服装
これから卓球をはじめる方にとって、まず気になるのが服装です。卓球チームによっても異なりますが、基本的には動きやすい服装が好まれます。特に卓球は、素早い動きをするスポーツです。汗もかきやすく、腕を使用するため、半袖がよいでしょう。
また、汗をしっかり吸収するためにも、吸水性や速乾性に優れたTシャツが望ましいといえます。多くのメーカーが販売するスポーツ用のTシャツは、汗をよく吸う生地が使用されています。練習時の服装は、チームによってはオリジナルTシャツで行うところもあります。
チームだけのTシャツは、メンバーのモチベーションの向上にもつながります。さらに協調性も高まる傾向があるのでおすすめです。ズボンも動きやすいように、短パンを使用するところが多く見られます。
腕だけではなく、フットワークも卓球では必要だからこそ、動いて不快にならない程度の服装が好ましいといえるでしょう。靴や靴下はチームで揃えているところもありますが、体育館などでも使用するシューズでも問題ありません。
2.卓球ユニフォームの規定
大会に出場するときは、練習着ではなくユニフォームを準備しましょう。ユニフォームにはさまざまな規定があるので、注文するときなどは注意しなければなりません。ここでは、卓球ユニフォームの規定についてご紹介します。
2-1.JTTA公認マークを付ける
JTTAとは、日本卓球協会のことを指します。JTTA 公認マークは、JTTAが主催する大会では必ず付けておかなければならないマークであり、なければ大会に出場できません。卓球用で販売されているものであれば、基本的に付けられています。
ユニフォームをオーダーする際は、シャツの袖とパンツの前面に取り付ける必要があります。付いているかを必ず確認してから着用することをおすすめします。
2-2.ユニフォームの色にも気を付ける
卓球で着用するユニフォームは、ボールの色と明らかに異なっていなければなりません。卓球で使用されるボールは、どのスポーツよりも小さいといえます。コート上で見失わないためにも、ユニフォームには気を配りましょう。
たとえば白いボールを使う大会であれば、白色が少ないユニフォームの着用が必須です。白いボールでも使用できるユニフォームには、赤色のJTTA公認マークが付けられています。このマークは、大会の審判長が試合前に確認します。
使用できない場合は失格となるので、事前にチェックしておくとよいでしょう。
2-3.大会にはゼッケンが必須になる
大会に出場する場合、ゼッケンを背中に取り付けます。ゼッケンは安全ピンを利用するので、事前に準備しておきましょう。業務用で購入できる安全ピンはもちろんですが、卓球用にさまざまなデザインが販売されています。
チームで揃えた安全ピンなど、細部までこだわるのも楽しみのひとつです。
3.ユニフォーム選びのポイント
ユニフォームを購入する際、「種類やメーカーが多すぎて選べない」という方もいらっしゃるかもしれません。ユニフォームは規定を守ったうえで、ポイントを抑えれば、比較的安くて良質なユニフォームを購入することも可能です。
ここでは、ユニフォーム選びのポイントについてご紹介します。
3-1.素材を考える
ユニフォームで使用される素材はさまざまなものがあります。吸水性や速乾性に優れたもの以外に、伸縮素材や保温性に優れているものなど、自分に合った素材を選びやすいのが特徴です。汗をかきやすい方の場合は、吸水性と速乾性は必須といえます。
窮屈感に感じず、運動の妨げにならないことを優先するのであれば、身体にフィットする伸縮素材がよいでしょう。冬場などの寒くなる時期には、中綿が入った保温性に優れた服装などをおすすめします。
3-2.ディティールにこだわる
ディティールにこだわることで、より機能性やデザイン性に優れたユニフォームを選べます。たとえばウォーミングアップで使用する服の場合、袖口などにゴムを取り入れたものが多くあります。
これは、運動した際に袖口が邪魔にならず、動きやすさを重視した結果だといえます。また、フードが付いたユニフォームも存在しており、デザイン性を重視する方が好む傾向があります。
細部までこだわることで、機能性はもちろんのこと、愛着もわきやすいユニフォームになるでしょう。
4.まとめ
はじめて卓球をする方にとって、ユニフォーム選びはとても重要です。チームによってはすでに決まっていることもありますが、これから立ち上げるのであれば、細部までこだわったウェアを選ぶことをおすすめします。
「イルマックス」は、お好みにあった卓球ユニフォームを作成いたします。デザインはもちろんのこと、服に使用する素材も選べます。卓球ユニフォームをお探しの方は、ぜひ一度お気軽にご連絡ください。
プレゼントにおすすめのサッカーグッズとは?ベスト3を紹介

ワールドカップなど必ずといっていいほど盛り上がることからわかるように、サッカー人気は留まることを知りません。友人や知人の中にサッカーが好きな人がいた場合に、プレゼントとしてサッカーに関するものをチョイスすると喜ばれるでしょう。そこで今回はプレゼントとしておすすめのサッカーグッズをご紹介いたします。
1.おすすめその①レプリカユニフォーム
サッカーが好きな方に贈るものとしてまず間違いないグッズと言えるのではないでしょうか。レプリカユニフォームは実際に選手が着用しているユニフォームをベースに、機能性と引き換えに耐久性を向上させたコピー品のことです。コピーといっても偽物ではなく、オリジナルの製作者が携わっている正規品です。
日本代表に限らず、世界各国の代表ユニフォームに関してもラインナップされていますので、よほどマニアックなチームのサポーターでなければ問題ないでしょう。まずは事前にプレゼントする相手がどのチームを応援しているのか確認することが重要です。そして、サッカーが好きな方であればすでにレプリカユニフォームを持っている可能性もありますので、その部分に関してもさり気なく確認しておくといいでしょう。
レプリカユニフォームは、様々な用途で使えるという点もプレゼントとしておすすめのポイントです。まずは観戦時などに着ることでライブTシャツのように気持ちを盛り上げるために使用できます。その他にも耐久性に優れているという特徴がありますので、サッカーの練習着としても最適です。また、着用しなくても部屋に飾ったりするだけでもインテリア的な楽しみ方ができるのではないでしょうか。
2.おすすめその②スパイク
実際に休日等にサッカーを楽しんでいる方であれば実用性が非常に高いプレゼントとなります。サッカーにスパイクは欠かせないアイテムですので、プレゼントすることで必ず使ってもらうこともできます。有名スポーツブランドをはじめ、数え切れないほどのメーカーが販売していますので、見た目のかっこよさや機能性など、総合的に考えた上で選択するといいのではないでしょうか。
ただし、スパイクは靴ですのでサイズが非常に重要となります。どれだけ見た目や機能が素晴らしいものであっても、プレゼントする相手の足にあったサイズでなければ使用することができません。飾っておくという選択肢もありますが、履いてこそ意味があるアイテムですので、あらかじめサイズ感を確かめておく必要があります。また、好みのブランドがあるという場合も考えられますので、注意しなければなりません。
スパイクは靴底にスタッドと呼ばれる突起が複数ついており、形状にはいくつかの種類が存在します。近年では以下の4種類が代表的ですので、それぞれの特徴を理解しておくとプレゼント選びの際に役立つでしょう。
2-1.丸型
その名の通りスタッドが円形になっているタイプです。足への負担が少なく耐久性も高いのですが、グリップ力が少し劣るため踏ん張りが求められる場面にはやや弱いです。
2-2.ブレード型
ゆるやかな半月のような形をしたタイプです。グリップ性能が高いのですが、その分足への負担も大きいのが特徴です。
2-3.トライアングル型
スタッドがおにぎりのように三角形のタイプです。360度全方向へのグリップ力が高いという特徴があります。
2-4.ミックス型
丸型+ブレード型などのように、複数種類のスタッドが混在しているタイプです。グリップ力が高いだけでなく、足への負担も少ないため近年では採用している選手が非常に多い傾向にあります。
3.おすすめその③小物類
レプリカユニフォームやスパイクは値段もそれなりにするので、そこまで大袈裟でなくちょっとしたプレゼントにしたいという場合におすすめなのが小物類です。サッカーに関する小物類は非常に豊富で、例えば試合の際には脛当てを挟むという意味でも必要となるソックスをはじめ、練習や応援の際に汗を拭うために活用できるリストバンド、バッグやキーケースなどに付けることの出来るキーホルダーなど多岐にわたります。
小物アイテムの中でも鉄板とも言うべきアイテムが「タオル」です。種類が非常に豊富で、日本代表グッズですとフェイスタオルの他に、バスタオル、手ぬぐい、スポーツタオル、タオルマフラー、ミニタオルなどがあります。その中でもさらにデザインの種類が複数存在していますので、選択肢がたくさんあるというのも嬉しいポイントではないでしょうか。タオルを貰って困るというのはほとんど聞きませんので、万人受けするというのが最大の特徴と言えます。
また、ソックスの場合にはサイズを選ばなくてはならないものの、大抵の小物グッズはサイズを気にしなくてもいいというのもプレゼント選びが気楽にできるという意味でおすすめポイントと言えるでしょう。また、プレゼントをもらう側にとっても値段などがちょうどいい感じとなりますので、大抵の方に喜んでもらうことが出来るのではないでしょうか。
4.プレゼントの際の注意点
サッカーグッズをプレゼントする際の注意点ですが、第一に「サイズ」に気をつけなければなりません。レプリカユニフォームやスパイク、ソックスなどのように身に着けるグッズであればサイズが合わないと無駄になってしまいます。確認しなくてもわかるほど親しい間柄であれば問題ありませんが、そうでない場合には事前にさり気なく確かめておくようにしましょう。
5.まとめ
今回ご紹介したグッズを参考に、サッカー好きの方にプレゼントをしてみるのもいいでしょう。好きなもののグッズをプレゼントしてもらうというのは嬉しさも倍増するはずですので、きっと気に入っていただけるのではないでしょうか。「イルマックス」ではオリジナルのユニフォーム作成を承っていますので、贈る相手の名前と背番号入りユニフォームを作成する事が可能です。詳細はぜひお気軽にお問い合わせください。
サッカーを楽しむ上で欠かせない!様々なグッズをご紹介

サッカーは基本的にはサッカーボールさえあれば、プレイすることは可能です。しかし、プロのように本格的にプレイするとなると、ボールだけでは不十分で、用途に合わせて様々なグッズを用意する必要があります。そこで今回は、サッカーを楽しむ上で欠かせない各種グッズについて紹介します。
1.サッカーグッズその①ウェア
まず、ウェアは欠かせないグッズの一つです。季節や気温に応じた長袖や半袖のシャツなどで構いません。公式ユニフォームに近い素材やデザインなどのウェアを身に着けてプレイすれば、気分良くプレイに集中することが出来るでしょう。
そんなウェアには、試合のためのユニフォームだけでなく、練習用ウェア(ゲームシャツ)があるのをご存じでしょうか?試合用のユニフォームは、チーム名や背番号が必ず記載されていますが、練習用シャツの場合は不要なので記載は一切ありません。
そのためゲームシャツは自由なデザインながら、ウェアとしての役割がユニフォームと同等で、かつ価格もリーズナブルなど、メリットの多いウェアなのです。シャツだけでなくプラクティスパンツもあり、基本的にはシャツとセットでの販売が多いようです。
ですので、こだわりがない方であれば市販のセットを購入して、そのまま着ることもできます。また、有名なクラブチームのレプリカのゲームシャツ&パンツも販売されているので、気持ちを高めるために、好きなクラブチームのものを望んで着用する方もいるほどです。
特に小さなお子さんの場合は、機能性よりも見た目のかっこよさが重要となるケースが多いようです。お気に入りのデザインであるというだけで、プレイへのモチベーションを高める効果もありますので、まずは着たいと思うウェアを購入することが大切でしょう。
2.サッカーグッズその②シーズン別のアイテム
サッカーに季節は関係ありません。暑くても寒くても、当然のように試合や練習を行うことになります。そこで重要なのは冬場に着用する防寒アイテムです。夏場であれば最低限着用しなければならない枚数が決まってくるので、通気性や飲み物などでほてった体のクールダウンを促すことになります。
冬場は長袖やウィンドブレーカーなどで対応します。ただし、ベンチにいる時や休憩の際にはそれだけでは不十分なので、ベンチコートを使用します。試合や練習の際は重ね着しますが、運動が前提ですので、着込み過ぎないようにしなければなりません。
動いていない状態であれば着込んでも問題ありませんが、運動するとすぐに体温が上昇するため、適宜脱着出来るような防寒着がベストと言えます。その点、ウィンドブレーカーはとても脱着しやすく、ユニフォームや練習用ウェアの上から着るだけでいいので、手軽なグッズとなります。
ベンチなど基本的に動かない状態でいる時間が長い場合は、ウィンドブレーカーでは防寒が不十分なこともありますので、ベンチコートの使用がおすすめです。主流は丈が膝下まであるようなスタイルで、体温を極力逃さないようにする工夫がなされているタイプです。
ベンチコートは、ダウンコートとボアコートの2タイプがあります。ダウンコートはダウンやフェザーなどを使用しているため保温や防寒性にとても優れていますが、少し値が張ります。一方、ボアコートの場合は中綿やフリースを使用しているのでダウンに比べて保温性などは劣るものの、動きやすさや軽さが特徴です。自宅で洗濯できるのもメリットでしょう。
3.サッカーグッズその③小物アイテム
ウェアだけでなく、小物アイテムもいくつかあります。まずは「スパイク」。通常のスニーカーでは踏ん張りが効かず、満足なボールコントロールができない場合が多いため、サッカーのプレイに適した設計の専用シューズであるスパイクは欠かせません。
特徴は、靴底部分にスタッドと呼ばれる突起がついている点です。スタッドには固定式と交換式の2タイプがあります。固定式は、地形などに関係なくオールマイティに使えますが、スタッドがすり減った場合に靴ごと交換しなければなりません。もう一つの交換式は、地形などに応じてスタッドを付け替えることもできますし、すり減ってもスタッドの交換だけで済みます。
2つ目は「脛(すね)当て」です。サッカーではハイソックスを着用します。脛当てはソックスの内側に入るような形状をしており、スライディングされた際などに脛の怪我を防止する役割があるのです。
その他にも、練習試合などで活躍する「ビブス」というメッシュ素材のノースリーブがあります。番号がついており、練習試合とはいえ選手を区別できるようになっています。練習着の上から着るだけでいいので、手軽で実用的と言えるでしょう。
4.機能性とデザインどちらで選ぶか
サッカーグッズを選ぶ際のポイントとしては、機能性とデザイン性という2つの要素があります。機能性の高さは、円滑にプレイするためのサポートになります。高機能性はデザインより重視すべきと思われがちですが、デザイン性の高さはプレイへのモチベーションに影響します。
また、見た目のかっこよさが、プレイスキルに少なからぬ影響を与えることもあります。サッカーグッズは、機能性とデザイン性のバランスの良さが、最も大切と言えそうです。
5.まとめ
サッカーを楽しみながらプレイするために必要なグッズは、このようにたくさんあります。「イルマックス」ではゲームシャツをはじめ、ベンチコートやビブス、ソックスなど各種サッカーグッズを取り扱っております。ぜひお気軽にお買い求めください。
ブレのないサッカーを楽しむために欠かせない「競技規則」について
どのスポーツにもルールや決まりごとというものがあります。サッカーに関してももちろん存在しているのですが、それを「競技規則と呼びます。なんの決まり事もない状態ですと試合を成立させることができませんし、そもそもスポーツとして成り立ちません。それを防ぐためのものが競技規則ですので、詳しくご存じない方のためにご紹介いたします。
1.競技規則とは
競技規則というのは、サッカーのルールや決まり事をまとめたもののことです。サッカーは世界中で親しまれている有名スポーツの一つですが、全く同じように楽しむことができているのは競技規則によって基準となるルールが決められているおかげというわけです。もし競技規則がなかった場合にどうなってしまうのかというと、ローカルルールのように地域などによって独自の決まり事が生まれ、極端な話サッカーとは別物の球技になってしまいかねません。サッカーというものはこういうルールで行うことを指していると認識してもらうことによって、言葉が通じなかったとしても同じルールのもと楽しむことが可能となります。
サッカーの競技規則は国際サッカー評議会(IFAB)と呼ばれる機関によって定められており、日本においては公式WEBサイトより日本語に翻訳された状態のものをデータで確認することが可能となっております。そのためいつでも世界共通の競技規則に則ってプレーすることが可能となっているというわけです。
その歴史ですが、始まりは1863年に遡ります。イングランドサッカー協会とロンドンのクラブが会議やミーティングを重ねた結果、統一ルールが作成されたのでした。イングランドからイギリス全土へと広がりを見せていく中で各地にサッカー協会ができ始めましたが、いつしかお互いの認識しているルールに若干の違いやズレがあることが判明することとなります。そこで、ルールに関する調整などを行う機関として「国際サッカー評議会」が発足したことによって、今日の競技規則へとつながっていくことになるのです。
2.定期的に改正される
当然のことかもしれませんが、競技規則は定期的に内容が更新されています。その理由としては様々ありますが、基本的には試合を無駄なくプレーするために、既存のルールで不備が見つかった場合などが挙げられます。単年度の11月実施される「年次事務会議」と翌年2月末に実施される「年次総会」によって最終的に決定されることとなり、然るべきタイミングで規則として反映されるというわけです。
競技規則の改正は簡単にはできない仕組みとなっています。投票式で決定するのですが、投票資格の内訳としてはFIFAが4票、イギリス本土にある4つの協会が各1票の計8表となります。最終的に討議されたルール改正に関して6票以上を集めたものが決定となります。この仕組みによって、FIFA側と協会側が自身の仲間だけで投票することで改正を決定することができませんので、独裁的な行為をあらかじめ無効にしているというわけです。
3.競技規則の内容
競技規則には具体的にどのような内容が決められているのか気になるところではないでしょうか。そこで代表的なものをご紹介しましょう。
3-1.ピッチや選手、審判員に関するもの
まずは試合をするためのピッチに関する細かい規定が決められています。例えば、ピッチの表面を覆う芝のタイプはどうしてもという場合を除き天然でなければならないということや、芝の色、ピッチ上に引かれている各種ラインのサイズ感などが挙げられます。また、ピッチ上にある様々な箇所の正式名称や、ゴールそのものの高さや奥行き、幅などに関しても記載されているのです。さらにボールに関しても表面の外周や重さ、空気圧に至るまで基準が設けられています。
3-2.試合時間やプレーに関するもの
試合時間が45分×2と15分のハーフアップであるということや、試合の始まりを告げるキックオフの際にコイントスで決めるなど、具体的にプレーに関係してくる部分となっています。得点がカウントされる基準についてももちろん記載されており、「ゴールキーパーが相手のゴールにボールを直接投げ入れた場合、ゴールキックが与えられる。」などと言った普段あまり意識していない規則なども存在しているのです。
3-3.ファウルやキック、スローインに関するもの
こちらもプレーに関するものに含まれるでしょう。スライディングなどによって審判員にファウルの判定がされる際の基準となる項目が定められています。押したり蹴ったり飛びかかったりなど、過度な力によって行った場合には直接フリーキックが与えられるということに始まり、手を使ってしまった際に問題のないシチュエーションや反対に反則とみなされる明確な基準についても記載されています。
4.審判員のためのガイドラインも含まれている
競技規則には審判員の方向けのガイドラインも記載されています。主審と副審がいますが、それぞれ試合中に正しくジャッジするために適した位置取りや、試合展開ごとの理想的なポジショニングが決まっています。試合の進行を妨げてしまうことなく、ファウルなどが発生した際には、正しい判断が出来るようにしっかりと目視できる状況を頭に叩き込むことで、優秀な審判員へと成長することも可能ではないでしょうか。
特にサッカーの場合には判断が難しい状況もありますので、ガイドラインがなければ崩壊してしまいます。細かく確認することによって、常に正しい判断基準を身に着けるといいのではないでしょうか。また、スライディングによるファウルの際などに、された側の選手の痛がり方が本当かどうかという部分に関してはガイドラインにも記載が難しい部分でしょう。競技規則はあくまでもルールブックとなりますので、直感での判断が求められる状況においては経験が必要となります。
5.まとめ
サッカーの競技規則は世界中で同じルールに則ってプレーするために欠かせないとても重要なものです。服装に関しても、特に色のことは細かい決まりがありますので、あらかじめ把握しておくといいでしょう。「イルマックス」は競技規則に則したゲームシャツやポロシャツなどのウェアを取り扱っていますので、興味をお持ちでしたらお気軽にお求めください。
今さら聞けないサッカーの歴史について!詳しく解説

今となっては非常に有名なメジャースポーツとなっているサッカーですが、その歴史やどのようにして日本でも親しまれるようになったのかということについて、ご存じない方は多くいらっしゃるのではないでしょうか。ルールやチーム、選手などについては詳しい方が多いにもかかわらず、意外ですよね。そこで、今回はサッカーの歴史について詳しくご紹介いたします。
1.サッカーとは
サッカーというのは、足を使ってボールを蹴ることで行う球技のことです。フットボールと呼ばれることもあります。
まず試合をするフィールドですが、105m×68mと決まっており、中央のハーフウェイラインを境として自陣と敵陣が分かれることとなります。ハーフウェイラインの中央にはセンターマークがあり、そこから半径9.15mの円をセンターサークルといい、試合開始はこの場所からキックオフして始まります。ボールをパスで繋いでいき、相手ゴールへとシュートすることで1点の得点が加算され、最終的に得点が多いチームの勝利となります。
原則として、選手はボールを足で蹴ることしかできません。ただし、フィールドの外周であるタッチラインの外に出てしまった場合に、両手を使ってフィールド内へボールを投げ入れるスローインの際は例外となります。また、チームに1名だけ存在するゴールキーパーに関しては、常に両手を使うことが許されているため、これも例外といえるでしょう。
試合時間は原則90分間で、前半後半45分ずつに分かれており、前半と後半の間には15分のハーフタイムが設けられています。
ちなみに、試合を観戦していると「ロスタイム」という言葉をよく耳にするかと思いますが、これはサッカーの試合時間カウントの決まりに起因しているものです。90分間の試合時間中、選手が怪我をしたりファールとなった場合など、プレイが止まっている状況であっても、カウントを止めません。そのため、実際にプレイする時間は90分以下になってしまうので、それを補う意味として用意されている時間がロスタイムというわけです。極端な話、怪我やファールなどプレイが中断する要素が一切なければ、90分間のみ、ロスタイムなしで試合終了となるのです。
2.諸説あるサッカーの起源
そもそも、サッカーというスポーツがどのようにして誕生したのかということですが、実のところはっきりとしているわけではありません。そのため諸説があるのですが、中でも有力とされている説についてご紹介したいと思います。
2-1.中世イングランド起源の説
諸説の中でも最も有力と言われている説です。8世紀頃の中世のイングランドが発祥であるとしている説のことで、その当時、イングランドでは戦争で勝利した際に、勝利の証として切り取った相手側の将軍の首を蹴って遊んでいたことが起源とされています。今では考えられないほど残酷な行為のように思えてしまいますが、その当時としてはまかり通っていたことのようです。その後首を蹴るだけでなく、目的の場所まで蹴って運ぶ様に変化し、首ではなくボールへと変わるなど進化を遂げてきたというわけです。
2-2.イタリア起源の説
イタリアの8世紀ごろに始まった、お金をかけてボールを蹴り合う遊びである「カルチョ」を起源としている説です。現代ではトトカルチョというものがありますが、その語源であるとも言われています。イタリアの方にとっては古くから身近に存在していた遊びであることから、起源として信じられているのです。
2-3.中国起源の説
中国で紀元前300年以上前に遡るほどの歴史ある「蹴鞠(しゅうきく)」という遊びをベースとしているという説です。日本でも蹴鞠(けまり)として伝わってきた遊びのことで、当時はあまりに熱中する人が大勢出たため、禁止令が発令されたと言われるほど人気であったことと、その歴史の長さから起源として有力視されています。
3.日本にサッカーが伝わったのは“明治時代”
起源については諸説あるものの、いずれも海外となりますので、一体どのようにして日本へと伝わったのでしょうか。
こちらについても諸説あり、一つは1872年に神戸で行った試合という説で、もう一つが1866年に横浜で行った試合であるという説となります。その後、神戸の師範学校(教員の育成機関)において取り入れられたことから、近畿地方で広がりを見せるようになります。それからは、近畿地方の師範学校の卒業生が全国各地で教員として配属されたことによって、全国的に中学校や高校などへと浸透していきました。
これにより球技としては普及していきましたが、全国的な知名度が爆発的に広まったのは、1993年の「Jリーグ発足」という出来事によるものでしょう。プロサッカーリーグということで、子どもたちが将来なりたい職業として挙げるなど、空前絶後の人気爆発でした。それからは日本におけるサッカー技術も徐々に向上していき、日本代表のワールドカップでの活躍や、印象的な敗北によって一般的に深く浸透したと言えます。
4.オリンピックの競技にも含まれています
サッカーが正式にオリンピックの競技として採用されたのは、1900年のパリオリンピックからです。しかし、実際にはその前の1896年のアテネオリンピック時点で、非公式ではあるものの試合は行われていました。その後、現在においても人気競技としてオリンピック競技の一つにラインナップされています。
オリンピックのサッカーでは、出場選手には「本大会開催前の12月31日時点で23歳未満」という条件が設けられており、一部例外を除けば25歳以上の選手は出場する資格がない状態となるのです。
5.まとめ
サッカーのルールや歴史について、これまで詳しく知らなかった部分を知ることができましたでしょうか?いまとなっては知らない人はいないくらい有名なスポーツの一つとなっていますが、最も古い説であれば、紀元前300年以上前から存在している球技ということになります。歴史を知ったことによってサッカーに興味を持たれた方は、創業40年という歴史ある「イルマックス」にてサッカー用品・ユニフォームを是非お買い求め下さい。







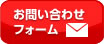

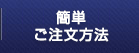









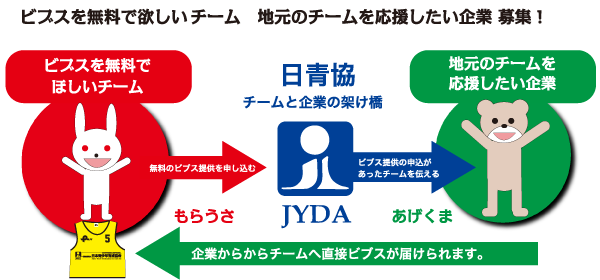
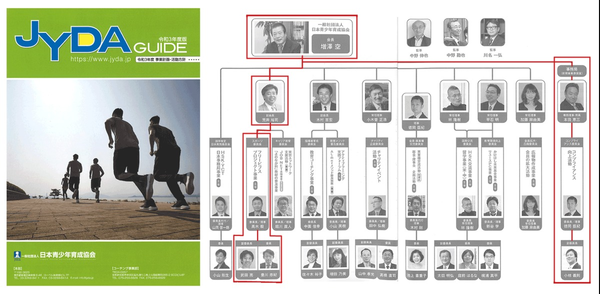








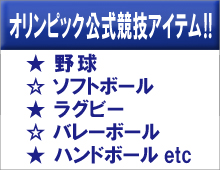
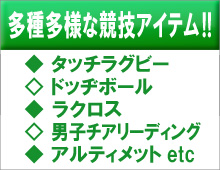
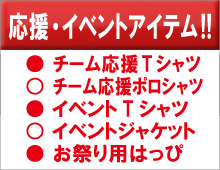


.jpg)